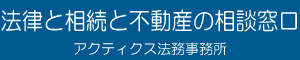相続放棄はいつから3ヶ月以内に手続きが
必要なのか調べてみた!
Menu
- 熟慮期間とは?
- 「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは?
① 「死亡を知ったとき」からだけではない
② 相続人が配偶者や子のとき
③ 相続人が父母や兄弟姉妹のとき - 「特段の事情」がある場合には、熟慮期間は「相続財産の存在を知ったとき」から始まる
① 例外を認める「特段の事情」とは?
② 「相続財産が全く存在しないと信じたこと」とは?
③ 「相続財産が全くないと信じたことについて、相当な理由があること」とは? - 例外は必ずしも認められるわけではない
1.熟慮期間とは?
POINT
- 熟慮期間は、原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
- 熟慮期間中に、相続放棄や限定承認の手続をしなければ、単純承認したことになる
相続放棄をするには、熟慮期間内にする必要がある
民法915条で、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない、としています。
そして熟慮期間とは、この相続を知ったときから3ヶ月以内の期間のことで、相続人は、期間内に被相続人の財産を調査したうえで、相続放棄や限定承認をするのであれば、その旨を家庭裁判所に申請して、認めてもらう必要があるのです。
相続放棄や限定承認の手続をせずに、熟慮期間が経過すると、単純承認したことになり、その後に相続放棄等の手続をすることはできません。
2.「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは?
POINT
- 「相続の原因である被相続人の死亡を知ったとき」かつ「自分が法定相続人(法律上の相続人)であることを知ったとき」から、熟慮期間は始まります。
- 法定相続人は、被相続人が死亡したときの家族構成や相続放棄の有無などによって異なります。
被相続人の死亡を知ったときからだけではない
では、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とはどのような意味なのでしょうか。文言を解釈すれば「自己のため」の「相続開始」があったことを知ったときからということになりますので、
①相続開始の原因の事実を知ったとき
相続は、死亡によって開始する。(民法882条)とされていますので、原則、被相続人が死亡した事実を知ったときが「相続開始」があったことを知ったときとなります。
②自分が被相続人の法定相続人であるということを知ったとき
誰が法律上の相続人となるかは、民法886条~895条で定められています。法定相続人は、被相続人の死亡時の家族構成や相続後の先順位の相続人の放棄や廃除、欠格などの事由によって、変更されることがありますので、それらの事項を踏まえ、自分が法律上の相続人となったことを知ることが、「自己のために」という意味になります。
相続人が被相続人の配偶者や子のケース
POINT
- 配偶者や子は、被相続人の死亡の事実を知ったときから熟慮期間は始まります。
被相続人の配偶者や子は常に相続人となります。また、子が被相続人より先に死亡しているときは、その子の子(被相続人からみれば孫に当たる者)、さらにその子の子(ひ孫に当たる者)は相続人となります。よって配偶者や子は、②の要件は常に満たすことになるので、①の要件を満たしたときに、自己のために相続開始があったことを知ることになります。
つまり、配偶者や子(子が先に死亡のときはその子など)の熟慮期間は、「被相続人の死亡の事実を知ったとき」から始まることになります。
相続人が被相続人の父母や兄弟姉妹のケース
被相続人に子や孫などがいないとき
POINT
- 父母や兄弟姉妹は、「被相続人の死亡の事実を知ったとき」かつ「先順位の相続人がいないことを知ったとき」から熟慮期間は始まります。
被相続人に子や孫などがいない場合には、父母や祖父母などの直系尊属が次順位の相続人となり、さらに直系尊属も生存していないときには、次々順位として兄弟姉妹が相続人となることが民法の規定によって定められています。法定相続人について詳しくはこちらを参考にしてください。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
民法の規定に従うと、父母が法定相続人となるには、被相続人に子や孫がいないことが必要ですし、兄弟姉妹が法定相続人になるには、被相続人に子や孫、父母、祖父母がいないことが必要になります。
よって、父母や祖父母の熟慮期間は、「被相続人の死亡の事実を知ったとき」と「被相続人に子や孫がいないことを知ったとき」の要件を満たしたときから始まることになります。同様に兄弟姉妹の熟慮期間の始期は、父母の場合のときの2つの要件に加えて、「被相続人の父母や祖父母などが生存していないことを知ったとき」となります。
先順位の相続人に相続放棄や廃除、欠格がある場合
POINT
- 父母や兄弟姉妹は、「被相続人の死亡の事実を知ったとき」かつ「先順位の相続人が相続放棄等の理由で相続人でなくなった事実を知ったとき」から熟慮期間は始まります。
相続人が相続放棄をしたときは、その相続人ははじめから相続人ではなくなります。また相続人となるべき者に欠格事由がある場合には、相続人となることはできません。さらに相続人に対して廃除の規定が適用されると、相続権を失うことになります。
そして先順位の相続人となるべき者が、相続放棄、廃除、欠格等の理由によって、相続人ではなくなった場合には、その相続する権利は、民法889条に規定されている次順位の相続人に移ることになります。
このような事由によって相続人となった者の熟慮期間は、「被相続人の死亡の事実を知ったとき」と「先順位の相続人が相続放棄や廃除、欠格となった事実を知ったとき」から始まることになります。
3.「特段の事情」がある場合には、熟慮期間の開始を遅らすことができる
POINT
- 最高裁では、相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、このように信ずることに相当な理由がある場合には、相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときから、熟慮期間は始まるとする例外を認めています。
相続人は、自らの相続について、熟慮期間である3ヶ月以内に、限定承認又は相続放棄の手続をしない場合には、相続を承認したことになり、原則、期間経過後は、相続放棄の手続をすることはできません。そして熟慮期間は、相続人となるべき者が「被相続人の死亡の事実を知ったとき」かつ「自らが法律上の相続人となった事実を知ったとき」から始まります。
しかし、相続人は相続財産が何もないと信じたところ、熟慮期間経過後に、被相続人の債権者からの相続債務の請求などによって多額の借金が判明するなどのトラブルが発生することも少なくありませんでした。そこで裁判所では、「特段の事情」がある場合限って、熟慮期間の始期を遅らせる例外を認めています。
例外を認める「特段の事情」とは?
POINT
- 「相続財産が全く存在しないと信じたこと」かつ「このように信ずることに相当な理由がある場合」には、特段の事情があるとしています。
最判昭59年4月27日の裁判例では、相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、このように信ずることに相当な理由がある場合に、相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときから、熟慮期間は始まるとするのが相当であると判断しました。
つまり熟慮期間の始期は、原則として、「被相続人の死亡の事実を知ったとき」かつ「自らが法律上の相続人となった事実を知ったとき」からとなるのであるが、例外的に相続財産が全くないと誤信していいたために相続放棄の手続をとる必要がないと考えて熟慮期間を経過した場合には、その誤信につき過失がないことを条件に、熟慮期間の始期を相続債務の債権から請求を受けるなどして、相続人が相続財産の認識をしたときからとなります。
「相続財産が全く存在しないと信じたこと」とは?
POINT
- 「自己の相続」について相続財産が全く存在しない場合も認められる事案もある
相続財産が全くない信じた場合とは、文言どおりに被相続人が残した財産や債務が全くないという事案に限られず、その範囲を拡大するような裁判例がいくつかあります。
生前に被相続人が公正証書遺言によって、負債を含んだ遺産の全てを一人の相続人に相続させることになっていて、自らは相続するプラス財産もマイナス財産も全くないと考えて相続放棄の手続をしなかった事案では、被相続人の死亡時に、債務などの相続財産が存在していることに認識があったとしても、債務の催告を受けたときから熟慮期間は進行するとしました。(東京高決平成12年12月7日)
相続人が被相続人の死亡時に、遺産としての不動産の存在を認識していたとしても、当該不動産は他の相続人が相続する等のため、自己が相続すべき遺産がないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、被相続人の積極財産及び消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったものと解するのが相当であるとしました。(名古屋高決平成11年3月11日)
一方、相続人が自己のために不動産等の財産を相続したが、その後、相続債務である第三者に対する保証債務が存在することが判明した事案においては、熟慮期間の始期を遅らす例外は認められませんでした。(高松高決平成13年1月10日)
東京高裁も名古屋高裁の裁判も、相続財産が全く存在していない訳ではなく、むしろプラス財産またはマイナス財産が存在していたことは相続開始時に知っていた事案です。しかしそれらの相続財産は他の相続人が全て承継することになっていたので、自分は一切、相続しないものと考えていたため、自己のための相続財産は存在していないという認識が認められています。
高松高裁の裁判のように、ただ単に、相続時に相続債務の存在を知らなかったというだけでは、特段の事情は認められないと考えられます。(この事案では、相続を単純承認した後に相続放棄を求めているものですので、むしろ民法919条2項の規定に基づく相続の承認について錯誤を原因とする取消ができるかどうかということになると考えられます。)
「相続財産が全くないと信じたことについて、相当な理由があること」とは?
POINT
- 被相続人とは別居していたほうが認められやすい?
次に「相続財産が全くないと信じたことについて、相当な理由があること」について、検討してみます。昭和59年判決では、相当な理由として、「被相続人の生活歴、被相続人との相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて」判断しています。そしてこの事案では、相続人は被相続人とは、10年以上も別居し、親子間の交渉が全く途絶えており、相続債務の原因が生じたのも、別居後のことであったというものでした。
その後の裁判例を見てみると、全く親子間の交流がないということまで求められているわけではないようです。婚姻後に別居して、被相続人との交流がお盆とお正月など1年に数度程度ある場合についても、相当な理由があると判断されているようです。
4.例外は必ずしも認められるわけではない?
最高裁の昭和59年判決では、「相続財産が全く存在しない」「被相続人との交流は全く途絶えていた」という事実を基にして、熟慮期間の始期を遅らせる例外を認めたのである。昭和59年判決を基にして、その後の裁判は、例外が適用される要件の範囲を拡大する傾向にあるのですが、事案によって全く認められないものもあります。
たとえば、東京高決平成14年 1月16日では、相続人らは相続人のうちの一人の者に取得させる旨の遺産分割協議を行った日を、相続の開始があったことを知ったときと認定されました。遺産を取得したのは相続人のうちの一人だけですし、他の相続人については、相続を受けていませんし、遺産分割協議をしたときには、相続人は相続債務が存在している認識はなく、相続人と被相続人は別居していました。このような状況であれば、自己のために相続すべき相続財産がなく、そのように信じることについて相当な理由があると判断され、債権者からの請求があった日を熟慮期間の始期として認めてもおかしくありませんが、この事案では認めてもらえませんでした。
いずれにせよ、相続放棄については上記のような例外規定の適否を検討することがないように、期日どおりに手続をすることをお勧めします。